

「私たちも家を買うぞ!」そう決意したはいいものの・・・具体的に何から始めたらいいの?と悩んでいるあなたへ
やるべきことがいっぱいあるのは、わかる・・・でも、明日から何ができる?

・マイホームを買おう!そう決意したけれど、まず何からすればいいの?
・家を建てるときのスケジュールが知りたい!期間はどのくらいかかる?
・家を建てる準備、明日から始められる具体的な取り組み方が知りたい!
・家が欲しいけれど、お金の計画ってどう考え始めたらいいのかな・・・
・最初にこれだけはしっかり準備しておくべき!というポイントが知りたい!
「家を買う」と言っても、お店に並んでいるようなものを買うわけじゃないし、何を用意したらいいんだろう?
まず誰に何をもちかけたら、家が買えるの?
スーパーでお米を買うのとは違って、「家を買う」イメージって漠然としていますよね。
ガンガン物件を見ていったほうがいいのか、とりあえず住宅展示場なのか。
不動産屋さん?ハウスメーカー?
住宅ローンもどうやって借りるの?
不慣れなことばかりで、明日から動こうと思っても、頭の中は「??」でいっぱい。
とりあえず、動き出しのはじめの一歩を、しっかり踏み出したい!
「これがテッパン!」のスタート、誰か教えて~!
家づくりを「なんとなく」で進めてしまうと・・・

・住宅メーカーはプロだし、きっといい提案してもらえるはず!知識がなくてもなんとかなる!
・情報収集の時間や手間を惜しんで、他人に任せっぱなし
・契約をしてしまったあとに「え?予算内じゃ、理想の家なんて全然建てられないじゃん!」
・大幅な予算オーバー、理想とはほど遠いマイホーム・・・。でも、もう後戻りできない・・・
・住み始めてから「本当の要望」に気づく・・・「こんなはずじゃなかった・・・」
広くて明るいリビングに、動きやすいキッチン。充実した収納スペース・・・
夢は広がるなぁ・・・。
新しくてピカピカのマイホームをイメージするだけなら楽しいのに。
いざ行動しようと思うと、家づくりも資金計画もなんだか難しい。
専門用語も多いし、知らないことばっかりで、面倒くさいなぁ。
「なんとなく」のイメージはあるし、とりあえず住宅展示場に行ってみたら、きっかけがつかめるかも!
ハウスメーカーの人はプロだし、こっちの希望をうまく聞き出して、いい提案してくれるよね。
事前準備もなく、住宅の知識もほぼゼロで住宅展示場に乗り込んだ結果・・・
ハウスメーカーの営業さんの意見に流されまくり。全部よく見える・・・。
手順もよくわからないものだから、相手のペースで進められてしまう。
せっかくの注文住宅なのに、気付けば営業さんのアドバイス通りの仕様ばかり。
打合せが進むにつれて、
「その変更は難しいですね」
「これは標準仕様でないので・・・」
「それはオプションになりますね」
契約後にあれこれ意見を伝えても、できないとか割高なオプションとか、そんなことばっかり。
予算も大幅にオーバー!にもかかわらず・・・
「私たちが建てたかったのって、こんな家だっけ・・・」
いざ住み始めると、動線も悪いし設備もイマイチだし、外観や内装も妥協したことばかり。
「家を建てる!」と決めたときは、あんなにワクワクしてたのに・・・。
大丈夫と言われて組んだ住宅ローンも、生活費をかなり圧迫してる。
全然、大丈夫じゃないじゃん・・・!
苦しいローン返済に、気に入らない家。
なんでこんなことになっちゃったんだっけ・・・。
ゴールまでスムーズに走るためには「スタート」が大事!
絶対に失敗したくないけれど、しっかり準備できるか不安でいっぱいなあなた。
大丈夫!初めての人でも「満足できる家づくりをスタートできるコツ」があるんです。
「面倒くさがり」で「計画性が低い」こんな性格の私でも、この方法で家づくりを始めて、最後はちゃんと「満足のできるマイホーム」を建てることができました!
理想の家を実現するために「自分たちで工夫しながら取り組めたこと」、本当によかったなと思います。
今回は「家づくり」の大まかなスケジュールとスタートでやるべきこと、「家づくりノート」や「住宅カタログ」をフル活用する方法について解説します。
きっと役に立つと思いますので、最後まで読んでみてくださいね。
家づくりが成功するかどうかは「自分たちがやりたいこと」がしっかりイメージできているかがカギ。
「知らないことは、もったいない」の気持ちで、効率的なスタートを切りましょう。
目標は「家族みんながしあわせに暮らせるマイホーム」!
理想の暮らしを手に入れるために、今から「家を建てる準備」始めてみませんか?
知っておきたい!家を建てるスケジュール

いざ「家を買おう!」と思っても・・・さて、どうやって動き出したらいい?
動き出す前に、まずは全体の流れをつかんでおくことが大事です。
「決意」してから「入居」するまで、大まかなプロセスを知って「現在地」を把握しながら動きましょう。
家づくりの手順は、ざっくりこんな感じです
「決意」してから「入居」するまでは、ざっくり4段階に分けられます。
①下準備
・情報収集
・希望条件の整理
・予算を決める
・家を建てる土地を決める
②設計
・建築プランと見積もりをもらう
・依頼する業者を決める(工事請負契約)
・住宅ローンの申請
・詳細打合せ・プランの決定
・建築確認申請・確認済証の交付
③工事
・地鎮祭(省略可)
・着工
・基礎工事
・上棟式(省略可)
・建物が完成(竣工)
・完了検査・検査済証の発行
・引き渡し
④完了
・登記
・住宅ローン融資開始
・入居
注文住宅に入居するまでの期間は、最短でも半年から7ヵ月、通常は1年くらいかかるイメージです。
建売住宅の場合、
①下準備
・情報収集
・希望条件の整理
・予算を決める
・物件を探す
②物件を決める
・住宅ローンの申請
・購入申し込み
・売買契約
・引き渡し
③完了
・登記
・住宅ローン融資開始
・入居
注文住宅と比べると、こざっぱりしてますね(笑)
建売住宅は、注文住宅よりも短期間で入居できるのがメリット。
買いたい物件が見つかれば、契約から入居までは3ヶ月くらいが目安です。
どちらにしても、スタートはまず「下準備」。
どんな準備をしていったらいいのか?確認していきましょう。
最も重視すべきは「事前準備」
注文住宅を建てるにしても、建売住宅を買うにしても、とにかく大事なのが
「どのくらいの予算で、どんな家に住みたいか?」
をはっきりさせておくこと。
家を買うんだから当たり前のことなんですが(笑)
この基本の部分をどのくらいガッツリ充実させておくかが、家づくり成功のカギになるんです。
あまり事前準備をせずに、なんとなく家づくりを進めようとしていませんか?
特に、注文住宅で苦戦してしまう人の多くが「準備不足」「なんとなく」で失敗しています。
「契約までの手順を間違ってしまい、住宅会社を変えたくても後戻りできない・・・」
「価格が安いと思っていたのに、追加オプションが割高で予算オーバー・・・」
「マイホームでの新生活が始まってから、本当の要望に気が付いた・・・」
などなど、「あのとき、知っていれば・・・」の後悔は「準備不足」が原因。
そうと分かっているのであれば、事前に対策しておけばOK!
「どのくらいの予算で、どんな家に住みたいか?」
このシンプルな質問を、どんどん掘り下げていきましょう。
「情報収集」「希望条件の整理」「資金計画」ここからスタートです!
事前準備の3本柱は「情報収集」「希望条件の整理」「資金計画」。
ベースに「情報収集」があって、その上に「希望条件」や「資金計画」が乗っているイメージです。
何もかもが初めての家づくり。
正しい情報が無ければ、正しい判断はできません。
そのくらい、家づくりにおいて「情報」は大事です。
たくさんの情報に触れることで「こんな家に住みたい!」のアイディアもどんどん広がりますし、
返済に無理のない資金計画や住宅ローンの組み方など、情報次第ではぐっとお得になることも。
どれもこれも「知っていたら、もっといい!」ことばっかりです。
はじめはチンプンカンプンだった「家づくりならではの知識」や「専門用語」にも、次第に慣れてきます。
知識不足で知らなかった「性能」や「仕様」、「設備」に出会えるかもしれないし、
想像すらできなかった「動線のいい間取り」や「コストダウンの方法」に気が付くかもしれない!
「知る」ことで、自分がまだ気付いていない理想のマイホーム像が見つかり、さらに快適な生活が手に入るかも!
そう考えると「情報を集めること」って、すごくワクワクしませんか?
住宅についての基本的な知識、希望条件の整理と優先順位付け、返済に無理のない資金計画。
この3本柱の基礎を固めておくだけで、家づくりのスタートからゴールまでスムーズに走り続けられるんです。
「情報収集」は後悔しない家づくりのカギ

はじめにしっかり取り組むべきは「下準備」。
「情報収集」の重要さもわかった。
よし!パソコンやスマホを前に・・・何から調べる?
迷ってしまったら、こんなポイントをヒントに調べ始めましょう!
意識したいのは「エリア」「予算」「デザイン」
まずは「住みたいエリア」についてリサーチ。
夫婦共働きなら、それぞれの通勤に便利な駅徒歩圏内?
お子さんがいるなら、保育園や幼稚園、小学校へのアクセスも視野に入れたいですよね。
どちらかの実家に近い場所なら、いざというときに助けてもらえて便利かも。
・子育て支援が充実している自治体か
・保育園や学童は激戦区じゃない?
・子供の医療費助成制度。何歳まで無料?
・小学校や中学校の状況
など、子供を育てやすい地域かどうかリサーチするのもおススメ。
住みたいエリアの目星がついたら、新築一戸建ての情報を検索。
自分たちが希望するエリアの相場観を知りましょう!
「予算」もしっかり把握しておく必要大!
家の購入に使えるお金がいくらかわからないと、住まい探しのスタートが切れません。
「予算」で一番重要なのは「自分たちが無理なく返せる返済額」を知っておくこと。
「借りられる額」と「無理なく返せる返済額」は意味が違うので要注意!
自分たちの「毎月の返済可能額」から、住宅ローンでいくら借入できるか?を試算するのがおススメです。
ちなみに、住居費は手取りの25%程度に抑えるのが目安。
もし手取り30万円なら7万5000円です。
住宅ローンシミュレーターで色々なパターンでの試算をしてみると、参考になりますよ。
調べがいがありそうなのが「家のデザイン」。
建売住宅なら、すでに建っている家を買うのでわかりやすいですよね。
でも、注文住宅だと「自分たちの理想の家」のイメージがかなり重要です。
家の外観から内装、性能や設備に至るまで「自分たちがやりたいこと」を細かくまとめ上げていく必要あり。
まずは「家のテーマ」を決めるのがおススメです。
北欧スタイル?モダン?ナチュラル?
SNSには外観からインテリアまで、おしゃれな写真がたくさんアップされているので、気に入ったデザインやアイディアはどんどんストックしておきましょう!
こういうお楽しみのリサーチがあると、情報収集のテンションも上がります(笑)
色々なハウスメーカーの得意分野やオリジナルの技術など、調べていくのも面白いですよ。
まずはこの3つのポイントを取っ掛かりにして、「広く浅く」情報収集をスタートしましょう!
「得意分野」で効率的に、欲しい情報を入手する!
情報収集の手段として、一番手っ取り早いのがインターネットやSNSですよね。
でもインターネットやSNSは、鮮度が高い情報発信は得意ですが、正確性に欠けるところがあるのが弱点。
家づくりのための情報収集の手段はたくさんありますが、それぞれ「得意分野」や「特徴」が違います。
「自分が欲しい情報」を得意分野とする手段を選べば、効率的に情報収集できる!
いくつかの手段とその「得意分野」ご紹介します。
・インターネット
⇒家づくりの基礎知識から、経験者のブログ記事、比較サイトなどもあり、とにかく手軽で便利。
情報の正確性に欠けるのが難点。「まずは手軽に情報収集をスタートしたい人」におススメ。
・住宅情報誌、書籍
⇒欲しい情報が1冊にまとまっている。専門家が監修しているため信頼できるのも◎。
工法や建材、間取りの工夫など、家づくりに関して専門性の高い知識が豊富なのも特徴。
・住宅会社のカタログ
⇒初めて家づくりをする人向けに作られているので、家づくりに必要な情報が網羅されていて、最新情報も早い。
ただ、自社のセールスが目的なので、デメリットは載っていない点に注意!他社のカタログと比較する必要あり。
住宅会社ごとの特徴がわかるので、情報収集と住宅会社選びが同時進行できるメリットも。
・チラシや広告
⇒近隣の土地や建売住宅の情報に強い!現在住んでいる地域の近隣を希望するのであれば、最新情報が手に入ることが多い。
しかし、情報の絶対数が少なく、売れ残り物件が多い傾向があるので注意。
・住宅展示場
⇒実際の注文住宅が体験できるのが強み。写真ではわからない部分を動きながら体験できる。
複数のハウスメーカーの建物を比較できるのも◎。ただ、モデルハウスは最上級グレードなので、参考程度に!
それぞれの手段の強みと注意点を把握した上で、欲しい情報を効率的に集めてください!
「必要な時までに、必要な情報を集め、整理しておく」ことが重要
家づくりがスタートすると、スケジュールに合わせて「期限付きで決めなければならないこと」がどんどん出てきます。
わずかな期間で、たくさんのことを決断しなければならないのが大変・・・!
経験不足のため、事前の予測が難しく、何でも後手後手になってしまいがちです。
だからこそ、必要になる情報を早めに準備、いつでも取り出せるように整理しておくことが大事。
集めっぱなしにしないことが、特に重要です!
・毎月の返済額、借入可能額はいくら?
・家づくりに使える自己資金額はいくら?
・頭金は入れる?
・金利は固定?変動?
・返済期間は35年?
・土地と建物の予算配分イメージは?
・借入先はどうする?
ただでさえ不慣れなジャンル・・・。
とりあえずで知識を入れて、急いで判断したら、失敗しちゃいそうですよね。
でもよくよく見れば、事前に準備しておけることばかり!
土地や家の詳細についても「希望」や「優先順位」は、自分たちで前もって準備や整理が進められますよね。
「はじめての挑戦」でいい結果を残したいのであれば、
「対策と準備はしっかり」
「必要なときに力を発揮できるコンディションを整える」!
なんかアスリートみたいですが(笑)
下準備の大切さのイメージ、伝わりやすいんじゃないかなと思います。
集めた情報を整理する「家づくりノート」のススメ

調べたときは「お~なるほど!」「よし!これでいこう」と思いますが、人ってすぐ忘れますよね。
聞きなれない単語も、まとめた数字も、すぐ忘れちゃう(笑)
せっかく集めた情報を、いつでも取り出せるようにするためにはどうしたらいい?
そんなときにおススメしたいのが「家づくりノート」です。
「家づくりノート」ってどんなもの?
「家づくりノート」は、そのまんまですが「家づくりに関するあれこれを、全部一冊にまとめたノート」です。
作り方や書き込む内容に決まりはありません。
でも、せっかくだから理想の家づくりに役立つ一冊にしたいですよね。
・今の住まいのここが不満!その理由
・新居でやりたいこと!どんな暮らしがしたい?
・住まいに求める条件、要望
・どんな設備や機能が欲しい?
・雑誌やカタログの写真を切り抜いて貼る!
・内容の優先順位をつける
・家づくりに使える総予算
・住宅ローンの計画
・頭金や諸費用にあてる自己資金
・予算の内訳はどうする?
・土地探し
・依頼する住宅会社を選ぶ
・打ち合わせ、相見積もり
・各種申請、手続きについて
「これは大切だな!」「これは調べておかないと!」と感じたことなど、思いついたことは何でも書き込んでOK!
家族の要望が変化したり、マイホームに取り入れたい新たな情報を見つけたら、どんどん更新していきましょう。
打ち合わせで、業者さんから言われた内容や注意点を書き残しておく議事録スタイルもあり。
「今後のスケジュール」や「解決しておきたい気になることリスト」の専用ページを設けるのもおススメ。
チェックシートとして活用すると、確認漏れも防ぐことができて安心です。
「家づくり」に関わるすべてのことを一冊のノートにまとめておく!
そうすれば、必要な時にサッと見直すことができますし、せっかく調べた情報を失うこともありません。
「家づくりノート」をつくるメリット
ものの整理整頓が苦手な私にとって、整理して失くさないでおけるだけでもメリットなのですが(笑)
はじめから「家づくりノート」を作って管理しておくことで、こんなにたくさんのメリットがあるんです。
・家族のライフスタイルを見直すいい機会になる
⇒今まで見過ごしてきた、家族の価値観や習慣など知ることができる
・集めた情報を整理しやすい
⇒必要なときにすぐ取り出せるのがいい!更新もしやすい
・色々なアイディアや気付きが生まれる
⇒せっかく思いついたアイディアも、書き込んでおけば忘れないで済む!
・費用や性能、メリットとデメリットなどを比較検討しやすい
⇒特にデメリットについてもしっかり調べる!
・実現したいイメージを明確に伝えることができる
⇒ハウスメーカーや工務店と打ち合わせするときにも、情報共有しやすく、イメージのズレも起きにくい!
・業者側にもいい緊張感を与えることができる
⇒打ち合わせのときに、内容をメモすることで「この人には適当なことができないぞ」と認識してもらえる
・家が出来上がったあとも、思い出の記録になる
⇒家族みんなで真剣に取り組んだ、いい思い出になります!
もちろん、ちょっとしたデメリットもあります。
・作るのが面倒
・時間も手間もかかる
・何を書けばいいか迷ってしまう
・必須事項が漏れてしまっても気が付きにくい
人によっては、こういう作業が面倒で苦手・・・という人もいますよね。
でも「面倒くさがり」「優柔不断」「計画性がない」こんな人ほど、整理整頓が苦手なんですよ(笑)
そんな私のような人ほど「家づくりノート」を作ることをおススメします。
こんな感じで作り始めましょう!
はじめに、ノートを用意しましょう!
「家づくりノート」におススメなのは、こんなノートです。
・持ち運びしやすいサイズ
⇒カバンの中におさまるB5~A4サイズのノートが使いやすいです。出かける時にも持ち歩くと、アイディアが思いついたときにすぐメモできます!
・方眼ノートが書きやすい
⇒配置図や間取りを書いたり、カタログの切り抜きを貼ったりするときにも、方眼ノートはきれいにできるのでおススメ!
・ページを増やせるバインダータイプ
⇒簡単にページを増やせるし、順番を入れ替えたりもできるので、一冊に管理しやすいです!
もし、ノートみたいなアナログなのが苦手だな~という人がいたら、スマホやパソコンを使ってもいいと思います。
無料のテンプレートをダウンロードすることもできるので、何を書いたらいいか迷ってしまう人におススメ。
必要な項目が出来上がっているので、初めてでもスムーズにノートづくりができます。
色々なテンプレートがあるので、自分が使いやすいものを探してみてくださいね。
家づくりノートの書き方に迷ったら、ブログやアプリを見本にしてもOK!
アプリを利用すれば、夫婦2人でいつでも編集、共有ができますし、字が汚いとか切り貼りが苦手という人でも、きれいにスピーディーに作成できます。
アプリで作成するのも、なかなか魅力的!
自分に合った方法で、家づくりに便利に活用できる「家づくりノート」を作ってみてくださいね。
「家づくりノート」を作るには、注文住宅のカタログがピッタリ!

住宅会社のカタログは、家づくり初心者向けに作られているので、実はとっても使いやすいんです。
最新の注文住宅事情から住宅会社の特徴まで、わかりやすく書かれているので、まさに「家づくりの情報の宝庫」!
活用しない手はありません。
アナログな「住宅カタログ」の需要が高まっているワケ
コーヒー片手にカタログをめくって、あれこれ考える時間。
ちょっといいですよね(笑)
今、アナログな「住宅カタログ」が人気な理由は・・・
・ネットには掲載されていない情報を得られる場合がある
・画面越しに見るよりも、建材の質感がわかりやすい
・「興味深い」「大事そうだ」と感じたページには、ふせんを貼ったり、書き込みをしておける!
・掲載できる情報に限りがあるので、メーカー側の伝えたいことがギュッとまとまっている
・家族とカタログを囲んでワイワイ雑談できる!
ふせんを貼ったり書き込みをしたり、さっと気軽にできるのはアナログのよさですよね。
家族会議の中心に、色々なメーカーのカタログが並んでいる様子はイメージしやすい!
無料で手軽に手に入れられて、内容も理解しやすい。
家族で話し合うときの材料としては、もってこいなんです。
注文住宅のカタログは、家づくりの情報の宝庫
「家づくりノート」を作るための資料としても、注文住宅のカタログはピッタリ!
・写真が豊富で、イメージが湧きやすい!
・わかりやすく編集されているので、知識の習得が効率的
・気になるページや写真を気軽に切り抜ける
・住宅メーカーの強み、技術力、提案力が比較しやすい
・大手ハウスメーカーのカタログを見ると、住宅のトレンドが一発でわかる!
住宅カタログのいいところは、具体的な写真や内容がコンパクトに分かりやすく、かつ丁寧にまとめられているということ。
情報量が多すぎて、何が何だかわからない・・・
何が正しい情報かわからない・・・
そんな事態に陥ることもなく、初めて家づくりをスムーズにスタートさせることができます。
イメージがどんどん湧いて、家づくりが楽しい!
このモチベーション、実はとっても大事なことですよね。
注文住宅のカタログから情報収集するときの注意点
情報収集を目的として「住宅カタログ」を見るとき、少し気を付けたい点もあります。
①「どんな家で暮らしたいか」という視点でカタログを見る
⇒「住宅会社を選ぶ」という視点ではなく、情報収集の一環としてカタログを見るようにしましょう!
②住宅カタログには「デメリット」は書かれていない
⇒他社のカタログとの比較は必須です!カタログに書かれていないものは、苦手やデメリットと思ってよし
③カタログに載っているのは「最上級グレード」
⇒良いものばかり見てしまうと、イメージと現実のギャップに驚くことも・・・
ひとことに「住宅カタログ」といっても、いくつか種類があるのでそれもご紹介!
・総合カタログ
⇒その名の通り、会社情報が一冊にまとめられているカタログです。
基本情報や商品ラインナップ、特徴、施工体制など、総合的な情報を網羅した内容になります。
・実例カタログ
⇒実際にその会社が施工した家の写真や暮らす人の感想など、実例が詰まったカタログです。
間取りや住んでみての実感、家へのこだわりなど、参考にしたい情報がいっぱい!
・住宅商品カタログ
⇒会社が手がける代表的なプランや、採用可能な設備、商品のコンセプトや特徴などが豊富に載ったカタログです。
・技術カタログ
⇒断熱性や耐震性、耐久性などの技術について、データや図解で解説されているカタログです。
独自の技術を活かした基礎や採用している構造、工法がまとめられています。
今、自分が見ているカタログは、4つのうちどの種類か?を意識して読んでみましょう。
それぞれの住宅会社が手がけている、家の特徴や違いが比較しやすいですよ。
カタログの特徴を活かして、効率的に欲しい情報を手に入れてください!
インターネットの一括資料請求が効率的!
家づくりの情報収集にとても役立つ「住宅カタログ」。
・会社のホームページから資料請求する
・住宅展示場で手に入れる
・一括資料請求サービスを利用する
インターネットで各会社のホームページから取り寄せてもいいのですが、いちいち情報を入力するのも面倒ですよね。
住宅展示場も、お子さんとイベントに参加しながら行ってみるのも楽しいですが・・・
カタログ目当てだとしたら、手間や時間がかかりすぎです。
そこでおススメなのが「一括資料請求サービス」。
フォームに必要な情報を入力するだけで、一度に複数のハウスメーカーや工務店から資料請求ができる優れものです!
住宅カタログだけでなく「間取りプラン」や「見積もり」まで作成してくれるサービスもあり、驚き。
家づくりに合わせて土地探しの提案もしてくれるので、初心者には心強いサポートですよね。
大手のハウスメーカーから地元密着の工務店まで、幅広い住宅会社から選ぶことができるので、比較しながら情報収集するにはもってこい!
「家づくりノート」の資料としても、とても優秀な「住宅カタログ」。
一括資料請求サービスを上手に活用して、効率的に情報収集をスタートしましょう!
>>「一括資料請求サービス」について、もっと知りたい方はこちらもどうぞ
↑↑↑
マイホーム購入の体験談が読めます!
まとめ
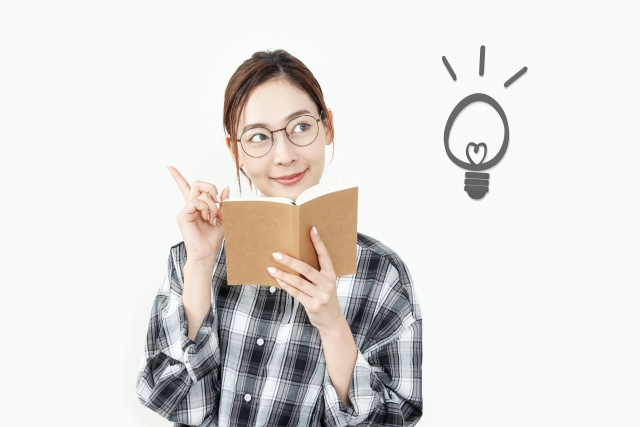
・家づくりで最初にすべき「事前準備」が超重要!
・「情報収集」「希望条件の整理」「資金計画」ここからスタート!
・「情報収集」で迷ったら「エリア」「予算」「デザイン」をヒントにリサーチ
・「自分が欲しい情報」を得意分野とする手段を選べば、効率的に情報収集できる
・「必要な時までに、必要な情報を集め、整理しておく」ことが重要
・集めた情報を整理するには「家づくりノート」がおススメ!
・「家づくりノート」を作るには、注文住宅のカタログがピッタリ
・住宅カタログを効率的に集めるには「一括資料請求サービス」を活用する
住宅メーカーはたしかに家づくりのプロですが、「あなた自身のこと」は、あなたが一番よく知っています。
信頼してお任せできる部分はプロに委ねる。
でも「自分がどうしたいか」は、あなたが伝えるしかない!
たとえば、花屋さんで「3,000円くらいの可愛い花束」とだけ依頼したとします。
5人の店員さんが作るとたら、出来上がるのは「5人とも全く違う花束」。
「あいまいなイメージ」と「少ない情報」でものを作ると、なかなか「イメージ通り」にはいきません。
花束だったら、全然自分の好みと違っていても「がっかり」で済みますが、家はヤバい!
価格は何千万円、これから長い間、家族と暮らす家です。
「伝える工夫」は大切。
写真を見せたり、入れて欲しい花材やラッピングの色を指定したりすれば「イメージに近い」花束ができますよね。
情報を「集める」、希望条件を「まとめる」、イメージを「伝える」。
家づくりの超重要ポイントには、割り切ってがっつり時間も手間もかけましょう!
「情報を知る」ことで、知らない頃には思いつきもしなかった、一段と快適な生活が手に入るかもしれません。
「知らないこと」はもったいない!
・「準備不足による家づくりの失敗」を回避することができる!
・家族みんなで「自分たちの理想の家」の情報を共有できるので、全員が満足できる家になる
・「どういう暮らしをしたいか?」具体的に、明確に伝えられるので、業者さんとの打ち合わせもスムーズ
・自分たちのイメージを見える化することで「理想の家」を建ててもらうことができる
・条件の優先順位や資金計画もバッチリ。後悔のない、安心して暮らせるマイホームが手に入る!
「家づくりノート」は集めた情報を整理して、家族や業者さんと情報共有もできる便利アイテム。
どんどんブラッシュアップしていくことで、家づくりのスタートからゴールまで、ずっと中心となって役立ってくれること間違いなしです。
時間も手間もかかるけれど、効率化できる部分はインターネットをしっかり活用。
無料でできる「一括資料請求サービス」、おススメですよ。
家族みんなで真剣に取り組んで、まとめ上げた「家づくりノート」。
きっと家が出来上がったあとも、思い出の記録になります。
「あれだけ悩んでよかったな」
振り返ったときにそう思えるような「家族みんながしあわせに暮らせるマイホーム」を手に入れてくださいね。
>>「一括資料請求サービス」について、もっと知りたい方はこちらもどうぞ
↑↑↑
マイホーム購入の体験談が読めます!